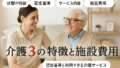「要介護1って、どんな状態なの?」「サポートの範囲や申請方法がよく分からない」「費用はいくらかかる?」──このように悩む方は決して少なくありません。最新の厚生労働省データによると、要介護認定を受けている高齢者のうち、約【22%】が「要介護1」に区分されており、特に75歳以上で1割以上が該当しています。
「食事や入浴、移動はほぼ自立だけど、一部だけ手助けが必要」、「家族の見守りや支援がどこまで必要?」。もし、ご自身やご家族が該当しそうだと感じたら、今この記事で、日々の困りごとを【制度・サービス・費用・事例】までまとめて確認できます。
公的統計をもとに、認定基準から生活援助の実態、サービス利用の具体的な流れまでを網羅し、「迷いや不安が具体的に解消できる内容」に整理しています。何をどこに相談し、どう備えるべきか――
今ここで要介護1の最新全体像を知ることで、「知らずに損をするリスク」や「無駄な手続き・支出」も未然に防げます。悩みの解決方法を、一緒に見つけていきましょう。
- 介護1とは何か|要介護1の定義と制度上の位置づけ(認定基準・区分について)
- 要介護1の生活状況と必要となる介助内容|日常生活動作の具体例と家族の支援ポイント
- 要介護1が利用できる介護サービスの全網羅|訪問介護・通所介護・短期入所の詳細と利用実態
- 要介護1の福祉用具と住宅改修|利用できる機器の種類、支給限度額、手続きのポイント
- 要介護1認定の実務|申請から判定までの流れと具体的なチェック項目
- 要介護1の認知症状況別ケア|認知症のある場合の生活支援・ケアプラン作成のポイント
- 要介護1の費用概観と給付金・負担軽減制度|具体的な金額目安と公的支援の全体像
- 利用者と家族の疑問に応えるQ&A集|要介護1について頻出する質問に専門家の回答を掲載
介護1とは何か|要介護1の定義と制度上の位置づけ(認定基準・区分について)
要介護認定制度の概要と認定区分の説明 – 介護1とは何か、要支援1との違いを詳述
要介護1とは、介護保険制度における「要介護認定区分」の1つで、日常生活を送るうえで一部の動作に介助が必要な状態を指します。具体的には、立ち上がるときや歩行、着替え、入浴、排泄といった場面で部分的なサポートが必要な方が認定されます。
下記の表は要支援と要介護の違いをまとめたものです。
| 区分 | 主な特徴 |
|---|---|
| 要支援1・2 | 基本的には自立だが、生活の一部に援助が必要。介護予防サービスが中心。 |
| 要介護1 | 身の回り動作で部分的な介助が時に必要。生活全般のサポートが求められる。 |
| 要介護2以上 | 介助の必要性が増し、ADL(日常生活動作)の多くで介護が必要な状態。 |
要介護1は、自立した生活に一部支援が必要なレベルであり、介護2や3ほどの重度の介護は必要ありません。要支援1との違いは日常動作への介助量の違いにあり、要介護1以上でより多様な介護保険サービスが利用可能となります。
要介護1の認定基準詳細(基準時間・調査項目・判定モデル) – 一次判定から審査会判定までの流れを明示
要介護1と認定されるためには、全国共通の認定基準に基づいた判定を受けます。市区町村に申請を行うと、認定調査員が「基本調査」と「特記事項」の聞き取り・観察を実施します。
調査項目には
-
身体機能の日常動作
-
認知機能
-
コミュニケーション能力
-
行動・心理面
などがあります。
要介護1の判断目安となる介護時間は「25分以上32分未満/日」が基準です。一次判定はコンピュータによる自動判定、その後に介護認定審査会による二次判定が行われ、医師の意見書も加味されて総合的に決定されます。
介護1級との違いと正しい理解 – 介護1とは誤認されやすい他用語との区別
「介護1」と混同されやすい言葉に「介護1級」がありますが、これは全く異なる制度を指しています。介護1級は障害者手帳などの等級(旧制度)であり、現在の介護保険制度の「要介護1」とは無関係です。
-
介護1:介護保険制度で定める要介護認定の最軽度の区分
-
介護1級:主に障害年金や障害者手帳で使用されていた旧等級制
この違いを正しく理解することで、申請時や相談時の混乱を防ぐことができます。
要介護認定申請の基本手順と必要書類 – 新規申請・更新の手続き詳細
要介護認定を受けたい場合、住民票のある市区町村へ申請を行います。申請時に必要なものは、
-
本人または代理人による申請書
-
医療機関名・主治医情報
-
介護保険被保険者証
-
身分証明書
申請後、認定調査と医師の主治医意見書作成が行われ、最終的に「認定結果通知書」が郵送されます。認定の有効期間は原則6か月ですが、状況により12か月のケースもあります。さらに、更新申請の場合も同様の流れとなりますが、早めの準備が安心です。
要介護1の生活状況と必要となる介助内容|日常生活動作の具体例と家族の支援ポイント
日常生活動作(ADL)における部分介助の具体例 – 食事・排泄・入浴・移動時の支援内容
要介護1とは、大小の生活動作に一部の介助が必要な状態を示します。自分でできることも多いですが、下記のように一部で支援が求められます。
| 生活動作 | 必要な介助例 |
|---|---|
| 食事 | 調理や配膳、食事中の見守りなど |
| 排泄 | トイレまでの付き添いや介助、後始末の手伝い |
| 入浴 | 浴槽への出入りの補助、洗体や着替えの一部 |
| 移動 | 室内での歩行時の支え、転倒予防の声かけ |
要介護1の方は、時間帯や体調によって自立度が変化しやすいため、家族がこまめに状況確認し、急な体調変化や転倒に配慮したサポートを行うことが大切です。専門職と連携しケアプランを作成することで、より安全で快適な自宅生活を維持できます。
身体機能・認知機能の特徴 – 要介護1にありがちな機能低下パターンと対応例
要介護1になる主な原因は、筋力低下やバランス感覚の低下、初期の認知症などが挙げられます。多くは以下の特徴を持ちます。
-
歩行が不安定で、段差や移動時にふらつきやすい
-
一部の身の回り動作に手助けが必要
-
物忘れや判断力の一時的な低下がみられることがある
-
長時間の活動や複雑な動作の疲労感が増す
| 機能面 | よくある症状 | 対応策 |
|---|---|---|
| 身体機能 | 筋力・バランス低下、歩行時の転倒 | 歩行器・手すりの設置、見守り |
| 認知機能 | 物忘れ、同じ質問を繰り返す | メモの活用、声かけ・確認の習慣化 |
進行を防ぐためには、リハビリテーション・軽い運動・生活リズムの維持が効果的です。介護サービスの利用と併用し、本人ができることは尊重しつつ、必要に応じて適切な支援を行うことがポイントです。
高齢者本人・家族が注意すべきリスクと予防策 – 転倒・誤嚥・認知症進行の兆候と対策
要介護1の方の日常には、さまざまなリスクが潜んでいます。以下の点に注意し、予防策を取り入れていきましょう。
主なリスクとその対策
-
転倒:室内の段差・カーペットなどのつまずきやすい場所を整理し、手すりや滑り止めを設置する。
-
誤嚥:食事の際はよく噛む・小分けにして飲み込む・姿勢を正しく保つことを意識する。
-
認知症進行:会話や散歩などの適度な刺激、服薬管理や予定表の活用で進行を予防する。
リスク管理は家族だけでなく、ケアマネージャーや訪問介護職員とも連携しながら進めましょう。疑問や不安がある場合は、地域包括支援センターなどの専門窓口への相談も有効です。本人の自立を尊重しながら「できること」と「必要な支援」をバランスよく見極めることが安全な生活維持につながります。
要介護1が利用できる介護サービスの全網羅|訪問介護・通所介護・短期入所の詳細と利用実態
居宅介護サービスで利用できる主なサービス一覧 – 訪問介護・訪問看護・生活支援サービスなど
要介護1の認定を受けることで、在宅で利用できる多様な介護サービスが提供されます。自宅での生活を支えるためには、必要な支援を受けることがとても重要です。以下の表は主な居宅介護サービスとその特徴、利用の目安です。
| サービス名 | 主な内容 | 利用の目安 |
|---|---|---|
| 訪問介護 | 日常生活の介助(食事・排泄・入浴・掃除など) | 週数回~ |
| 訪問看護 | 医療ケア・健康管理・服薬管理等 | 必要時 |
| 訪問入浴介護 | 入浴の支援・体調管理 | 月1~数回 |
| 福祉用具貸与 | 介護ベッドや手すり、歩行器のレンタル | 常時必要な場合 |
| 生活支援サービス | 掃除・洗濯・買い物など生活全般の手助け | 必要に応じて |
| ケアマネジャー利用 | ケアプラン作成・サービス調整 | 継続的 |
特に訪問介護は、要介護1の方や一人暮らしの高齢者にとって心強い支えとなります。ケアマネジャーに相談しながら、自分や家族の生活に合ったサービスを組み合わせて利用するのがおすすめです。
通所介護(デイサービス)の利用頻度・費用目安 – 要介護1に適したサービス内容と活用法
通所介護(デイサービス)は、要介護1の方にとって身体機能の維持や認知症予防、社会参加の場として効果的です。主な内容は、機能訓練、食事、入浴、レクリエーションなどがあります。
利用頻度は自治体やケアプランによって異なりますが、目安として週2~3回、必要に応じて増やすことも可能です。利用回数や費用目安は下記表をご覧ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| デイサービス利用回数 | 週2~3回(回数制限あり) |
| 1回あたりの費用目安 | 約700円~1,500円(自己負担1割の場合) |
| 主な内容 | 食事・入浴・機能訓練・リハビリ・送迎 |
デイサービスの利用で外出や交流の機会が増えることは、要介護1の方の日常生活に大きなメリットとなります。ケアプランに合わせた利用が安心です。
短期入所・宿泊サービスの概要と活用シーン – 認知症ケア含めた利用事例
短期入所(ショートステイ)は、数日から数週間施設に宿泊し生活全般の介護を受けるサービスです。家族の急な用事や介護疲れ防止のため、一時的な利用が広まっています。認知症の方でも利用可能で、安心して過ごせる環境が整っています。
短期入所サービスの活用例
-
家族が旅行や出張等で一時的に介護ができない場合
-
介護者の体調不良やリフレッシュが必要な場合
-
認知症状の悪化防止・見守りケアが必要な場合
利用費用は1泊2,000~3,000円程度(自己負担1割)となり、施設ごとに異なります。急な利用時もケアマネジャーへの相談で柔軟に対応が可能です。
複合型サービスや地域密着型サービスの特徴とメリット
複合型サービスとは、訪問介護・看護と通所サービス等を組み合わせたパッケージ型の支援です。地域密着型サービスでは、同じ地域内で提供されるため迅速な対応や安心感があります。
特徴・メリットリスト
-
一人暮らしや認知症の方に継続的な見守り支援
-
必要なサービスを柔軟に組み合わせ可能
-
地域情報の共有や緊急時の対応がスムーズ
自宅でできるだけ長く自立した暮らしを支える仕組みとして、要介護1から多くの方が複合型・地域密着型サービスを活用しています。ケアマネジャーと相談しながら最適な組み合わせを選ぶことが、より安心できる生活の実現につながります。
要介護1の福祉用具と住宅改修|利用できる機器の種類、支給限度額、手続きのポイント
要介護1で使える福祉用具レンタル・購入例 – 手すり、歩行補助具、車椅子などの具体例
要介護1に認定されると、介護保険を利用して様々な福祉用具のレンタルや購入が可能です。代表的な用具には、日常生活の自立をサポートするアイテムが多く含まれます。主な例は下記の通りです。
| 用具名 | 利用方法 | 主な用途 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 手すり | 購入可 | 立ち座り・歩行補助 | 室内の各所に設置、負担軽減に効果的 |
| 歩行補助杖 | レンタル | 屋内外歩行の安定 | 杖の種類も多彩、身体状況に合わせて選択 |
| 車椅子 | レンタル | 長距離移動サポート | 必要に応じて自走・介助タイプを使い分け |
| シャワーチェア | レンタル | 入浴時の転倒防止 | 介助付き入浴に安心、高齢者に人気 |
| ベッド用手すり | レンタル | ベッド昇降の助力 | ベッドスペースに合わせて設置可能 |
レンタル品は原則月額費用の1割負担で利用できます。状態や介護度によって適用範囲が異なるため、利用前にケアマネージャーと相談しましょう。
住宅改修費の助成内容と申請方法 – 手すり設置、段差解消、床材変更の事例と条件
要介護1の認定を受けることで、住宅改修費の一部を介護保険から助成してもらえます。特に高齢者の日常生活を支えるために実施される改修は、快適かつ安全な在宅生活へ直結します。
| 改修内容 | 代表的な事例 | 支給対象の条件 |
|---|---|---|
| 手すりの取付 | 廊下・トイレ・浴室 | 移動や立ち座りにリスクがある場合 |
| 段差の解消 | 玄関・室内の敷居 | 移動時のつまずきやすい場所 |
| 滑りにくい床材へ | 浴室・廊下の床材変更 | 転倒リスクの高い箇所 |
| 引き戸への交換 | ドアの開閉が困難な場合 | 車椅子や歩行器の利用者にも有効 |
申請手続きは、事前に市区町村の窓口に必要書類と改修内容の見積書を提出し、承認を得てから改修工事を進めます。改修後、領収書と工事写真の提出をもって費用助成が受けられます。
福祉用具と住宅改修の費用負担と保険適用範囲 – 支給限度額や自己負担の仕組み
福祉用具や住宅改修には介護保険による負担軽減制度が設けられています。制度内容を把握して計画的に活用することが重要です。
| 項目 | 支給限度額 | 利用時の自己負担 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 福祉用具レンタル | 月額約105,000円 | 1割(収入に応じて2-3割) | 限度額超過分は全額自己負担 |
| 特定福祉用具購入 | 年間10万円 | 購入時1割のみ | 例:入浴用椅子、ポータブルトイレ |
| 住宅改修費 | 20万円/生涯一回限り | 実費の1割 | 住居人ごとに支給 |
上記の支給限度内であれば、自己負担を抑えて必要なサポートが受けられます。また、要介護1の支給限度額や対象品目は定期的に見直しが行われるため、最新の情報を専門相談員やケアマネージャーと連携して確認しましょう。
介護保険適用の範囲外となる機器や改修もあるため、ご自身の状況に合わせて最適なサービス選択が求められます。
要介護1認定の実務|申請から判定までの流れと具体的なチェック項目
認定調査の内容と評価ポイント – 健康状態、身体能力、日常生活自立度の見方
要介護1の認定を受けるには、主に「要介護認定申請」「認定調査」「主治医意見書」「審査会による判定」のステップがあります。市区町村へ申請後、認定調査員が自宅や施設を訪問し、身体機能・認知機能・日常生活自立度を細かくチェックします。
調査項目は40近くに及び、以下のポイントが重視されます。
-
立ち上がりや歩行などの基本動作
-
食事や排泄、入浴などの日常生活能力
-
認知症の有無や、その程度
-
病歴や既往症
-
社会交流や自立度
調査内容は下記のように整理されます。
| 評価項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 身体的日常動作 | 立ち上がり、歩行、トイレ、入浴、食事 |
| 認知機能 | 会話の理解、日時や場所の認識 |
| 行動の安定性 | 徘徊や転倒、見当識障害の有無 |
| 生活の自立度 | 一部介助が必要か完全自立か |
調査時には、本人だけでなく介護している家族の話も参考にされるため、日常の様子を整理して伝えることがポイントです。
認定プロセスにおける注意点とよくある誤解 – 一次判定・二次判断、審査会の役割
認定プロセスには、一次判定(コンピューターによる自動判定)と二次判定(有識者による審査会)があります。多くの方が「一次判定のみで結果が決まる」と誤解しがちですが、実際には医師の意見書や本人・家族の状況も考慮し、人の目で最終判断が行われます。
以下の点に注意しましょう。
-
一次判定…全国共通の基準で自動計算。点数化されるため公平性が保たれています。
-
二次判定(審査会)…地域の医師や看護師、保健師などで構成される審査会が、個々の状況を慎重に審議します。
-
思い当たる症状や困りごとは、調査員や主治医に正確に伝えることが重要です。
よくある誤解として、「一度認定されると変更できない」「軽度でも介護1になる」といった情報がありますが、正確には状態の変化に応じて区分変更申請も可能です。
認定結果の活用法と更新手続き – 判定後のケアプラン作成との関連性
認定結果により、「自宅でどのようなサービスが利用できるか」が具体的に決まります。要介護1に認定された場合、ケアマネジャーと相談し、ケアプランを作成します。
選択できる主なサービス例は以下の通りです。
| サービス名 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 訪問介護 | ホームヘルパーが身の回りの介助を実施 |
| デイサービス | リハビリや入浴、食事などを日帰りで提供 |
| 福祉用具レンタル | 歩行器・手すり等の貸し出しで自立支援 |
| 住宅改修 | 手すり設置・段差解消など住環境整備 |
| ショートステイ | 短期入所で家族の介護負担を軽減 |
要介護認定は基本的に6か月ごとに見直しがあり、状態が変化した場合は速やかに区分変更申請が可能です。定期的にケアマネジャーと面談し、本人の希望や家族の状況を反映した最適なケアプランを随時作成し直すことが大切です。
要介護1の認知症状況別ケア|認知症のある場合の生活支援・ケアプラン作成のポイント
認知症を伴う要介護1の特徴と日常支援法 – 認知機能低下への対応策と症状別支援例
認知症がある要介護1の方は、記憶や判断力の低下による日常生活の困難が見られますが、身体機能の多くは比較的自立しています。主な特徴は次の通りです。
-
日付や場所を間違えることがある
-
軽度の物忘れや失念が頻繁に起こる
-
一人での外出や服薬管理に不安が残る
支援のポイントは、認知機能低下への具体的対応策にあります。例えば、日々のスケジュールはカレンダーやメモに記入し、視覚的に確認できる環境を整えると安心です。また、服薬や食事の管理は家族やヘルパーが定期的に確認・声かけを行い、間違い防止を徹底しましょう。
症状別支援例を下記でまとめます。
| 状態 | 有効な支援策 |
|---|---|
| 軽度の物忘れ | メモ・カレンダー活用、話しかけやリマインダー |
| 外出時の不安 | GPS付き見守り機器や同行サポート |
| 金銭管理の難しさ | 家族または信頼できるケアマネジャーによるチェック |
定期的な見守りと、本人の「できること」を尊重したケアが信頼のポイントです。
認知症なしの要介護1の支援策 – 身体機能低下中心の支援に特化したケア
認知症がない場合、要介護1の主な課題は立ち上がり・歩行・入浴などの身体機能の一部低下にあります。自力で多くの生活動作が行えますが、部分的な介助や安全確認は欠かせません。
身体機能低下中心のケア具体例:
-
高齢者向けの手すりや段差解消など住宅改修の実施
-
転倒予防のためのリハビリテーションや歩行訓練
-
入浴・排泄・着替えなど一部動作の支援
利用できるサービスを一覧化すると以下のようになります。
| サービス名 | 内容 | 利用例 |
|---|---|---|
| 訪問介護 | ヘルパーによる身体介護と生活援助 | 入浴、調理、掃除 |
| デイサービス | 日帰りの機能訓練・レクリエーション | 週3回利用しリハビリ |
| 福祉用具レンタル | 歩行器、手すり、ベッドなどの貸出 | 家庭内安全対策 |
日々のサポート内容をケアマネージャーが計画し、本人の自立支援を重視することが重要です。
一人暮らし高齢者のケーススタディ – 安全確保・見守り・緊急対応方法
一人暮らしの要介護1高齢者は、安全の確保と孤立防止が最大の課題です。緊急時の備えや日常的な見守り体制の構築が不可欠となります。
実際によく用いられている対策には以下のものがあります。
-
緊急通報システムや見守りサービスの導入
-
定期的に家族や近隣住民、地域包括支援センターが訪問
-
配食サービスによる食事の確保と安否確認
利用サービス・支援方法をまとめました。
| 支援策 | メリット |
|---|---|
| 緊急通報装置設置 | 転倒などで動けないとき即座に救助要請 |
| 訪問サービス活用 | 専門スタッフが安全・健康状態をチェック |
| 生活支援コーディネート | 地域の資源を組み合わせた柔軟なケア提供 |
本人のライフスタイルや要望に合わせて柔軟なケアプランを作成することが、安心した自立生活につながります。
要介護1の費用概観と給付金・負担軽減制度|具体的な金額目安と公的支援の全体像
介護サービス利用にかかる費用の実態 – 自己負担割合と費用モデルケース
要介護1に認定されると、多くの方が介護保険を利用して「デイサービス」や「訪問介護」「福祉用具レンタル」などのサービスを受けられます。介護サービス利用時の自己負担割合は原則1割となっており、一定以上の所得がある場合は2割から3割となります。居宅でのサービス費用の目安は、1か月あたりの支給限度額が約167,650円(2025年時点)です。ここで自己負担額を計算すると、1割負担なら約16,765円となるケースが多いです。
以下の表は主なサービス利用時の費用例です。
| サービス名 | 1か月の利用上限額目安 | 自己負担(1割の場合) |
|---|---|---|
| デイサービス(週2回〜3回) | 約40,000〜60,000円 | 約4,000〜6,000円 |
| 訪問介護(週2回) | 約30,000円 | 約3,000円 |
| 福祉用具レンタル | 約7,000〜20,000円 | 約700〜2,000円 |
利用状況やプラン内容によって費用は異なるため、ケアマネージャーと相談することが大切です。
公的給付金の種類と申請手順 – 利用者が実際に受けられる金銭的支援
要介護1の方が利用できる公的給付金には、介護保険からのサービス費用補助が中心となります。このほか、自治体独自の負担軽減策や高額医療・介護合算療養費制度なども活用できます。
-
介護保険サービス費用の補助:介護認定後、支給限度額までを公費が負担。自己負担は原則1割~3割。
-
高額介護サービス費:ひと月の自己負担額が一定上限を超えた場合、その超過分が後で払い戻されます。
-
福祉用具購入・住宅改修費の助成:手すり設置や段差解消などの改修、年間10万円を上限に原則1割負担で申請可能。
-
自治体の独自給付金:住んでいる市区町村によっては、さらに支援金などを受けられることもあります。
申請手続きは、まず市町村の「介護保険窓口」にて介護認定を受けることから始まります。認定後、ケアマネジャーを通じて必要なサービスや給付金の手続きを進める流れとなります。
要介護1と他の介護度との費用・サービス比較 – 費用差を示しながら比較検討可能に
要介護1と他の介護認定区分(特に要支援2・要介護2)では、支給限度額や受けられるサービス、費用負担に違いがあります。以下に主要な介護度ごとの違いを比較した表を示します。
| 区分 | 支給限度額(月額) | 利用できる主なサービス | 1割自己負担目安(最大利用時) |
|---|---|---|---|
| 要支援2 | 約110,320円 | 生活援助、軽度な訪問・通所 | 約11,032円 |
| 要介護1 | 約167,650円 | デイサービス、訪問介護等 | 約16,765円 |
| 要介護2 | 約197,050円 | さらに多くの通所・訪問等 | 約19,705円 |
要介護1は要支援2よりも幅広いサービス利用が可能で、費用負担の上限も高くなりますが、その分本人・家族の負担軽減効果が期待できます。介護度が変わればサービスの選択肢も費用も変化するため、定期的なケアプラン見直しと専門家への相談が役立ちます。
利用者と家族の疑問に応えるQ&A集|要介護1について頻出する質問に専門家の回答を掲載
認定手続きや介護サービス利用に関する質問 – 初めて申請する人の不安を解消
要介護1の認定を受けるにはどのような手続きが必要ですか?という質問が多く寄せられます。申請は市区町村の窓口や地域包括支援センターで行い、申請後は認定調査と医師の意見書作成が必要です。調査は生活の困難さや身体・認知機能を細かく確認し、認定区分が決定します。
ケアマネージャーは要介護度に応じてケアプランを作成し、本人や家族の希望・状態に合うサービス選定をサポートします。サービス利用開始までの流れは次の通りです。
-
申請受付
-
認定調査・医師意見書
-
審査・認定結果通知
-
ケアマネージャー派遣とケアプラン作成
-
介護サービス利用開始
初めての方でも戸惑いなく進められるよう、必要書類や相談窓口をしっかり案内しています。
福祉用具や住宅改修の相談に多い質問 – 実際に利用する際の疑問点カバー
要介護1で利用できる福祉用具とはどんなものですか?住宅改修はどこまで対応できますか?といった問い合わせがあります。
要介護1で利用が多い福祉用具は、歩行器・手すり・シャワーチェア・ベッド用柵など日常生活の安全と自立支援に役立つものです。レンタルや購入の違いも相談が多いポイントで、原則レンタルが推奨されますが、特定の用具は購入補助も適用されます。
住宅改修は手すり設置や段差解消、滑り防止床材などが多く、最大20万円まで支給限度額の範囲内で補助が受けられます。工事前に自治体へ事前申請が必要なので、間違いのない手続きを専門家が案内しています。
費用や給付、利用範囲に関するよくある質問 – 負担軽減やサービス選択のポイント明示
要介護1になると毎月もらえるお金や自己負担額はどうなりますか?サービス回数や利用できる範囲は決まっていますか?という疑問は特に多く寄せられます。
サービス利用の支給限度額は月額約166,920円(2025年時点)が目安で、自己負担は原則1割(一定所得以上は2〜3割)です。自己負担例として、訪問介護やデイサービスの利用時、2時間のサービスが約250円〜600円程度から利用可能です。
デイサービスの利用可能回数や費用例を表でまとめます。
| サービス内容 | 月間利用目安 | 自己負担の目安 |
|---|---|---|
| デイサービス | 週2~3回 | 1回600円前後 |
| 訪問介護 | 週2回 | 1回300円前後 |
| 福祉用具レンタル | 月1~数点 | 1種目100円台~ |
※地域や事業所により変動。支給限度額内に収まる範囲で柔軟に組み合わせ可能です。
認知症や一人暮らし関連の質問 – 特殊ケースにも対応できる安心感提供
認知症があっても要介護1に認定されることはありますか?また要介護1で一人暮らしを続けることは可能ですか?といった心配に対して、状態に合わせたきめ細やかな支援が用意されています。
要介護1でも軽度認知症の場合は日常生活の一部サポートを受けながら在宅生活が可能です。ケアマネージャーと協力し、訪問介護や見守りサービスの活用・福祉用具で自立支援を行います。一人暮らしでも生活安全のため次の工夫が重要です。
-
見守りや緊急通報システムの利用
-
配食サービス導入
-
定期的な家族・近隣の協力体制
-
必要に応じショートステイや施設利用も検討
認知症進行や身体状況の変化があれば、要介護度区分変更や他サービスへのスムーズな移行もサポートされています。本人と家族の安心を守る支援体制についても丁寧に説明されています。