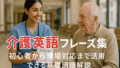高齢者同士が支え合う「老々介護」は、今や【世帯の4世帯に1世帯】以上で現実となっています。特に80歳以上の高齢者夫婦による介護は、認知症や身体の衰えへの備えが十分でないまま突入しがちです。厚生労働省の調査によると、介護が必要な人のうち身内による介護割合が【60%】を超え、その中で高齢者同士の介護「認認介護」も年々増加傾向にあります。
「体力に自信がなくなってきた…」「家族以外に頼れる人がいない」「施設の費用や手続きが不安」など、強い孤独感と先行きへの不安は多くの家族が抱いている現実です。実際、介護による肉体的・精神的な負担が蓄積し、共倒れや介護放棄が社会問題になっています。
しかし、強調すべきは、各自治体の相談窓口や在宅介護支援サービス、さらには公的な介護保険制度など、老々介護の「負担やリスク軽減」のための具体的な手立てが増えていることです。このページでは、実際のデータ・現場の声・活用できる社会資源をもとに、家族だけでは背負いきれない悩みやコストをどう乗り越えるかを、分かりやすく徹底解説します。
「今できる対策」「失敗しない選択肢」を知ることで、老々介護に伴う不安や損失を未然に防げます。まずは、「老々介護」とは何か、その現状と全体像から一緒に確認していきましょう。
老々介護とは何か-基本の定義と現状、最新の実態データ
老々介護の意味と読み方-「老々介護」と「認認介護」の違い・基礎知識
老々介護とは、高齢者自身がほかの高齢者の介護を担う状態を指します。読み方は「ろうろうかいご」です。要介護者の配偶者やきょうだい、時には友人なども該当します。近年は更に「認認介護(にんにんかいご)」と呼ばれる、認知症の高齢者が同じく認知症の高齢者を介護する状況も増加傾向です。
主な違いは以下の通りです。
| 用語 | 意味 | 読み方 |
|---|---|---|
| 老々介護 | 高齢者同士による介護 | ろうろうかいご |
| 認認介護 | 認知症同士による介護 | にんにんかいご |
高齢化が急速に進展する日本では、老々介護や認認介護の課題が大きくなっています。高齢者自身の体力や健康もリスク要因となるため、特別な支援が求められています。
最新の老々介護割合や推移-厚生労働省等の公的データに基づく現状分析
最新の厚生労働省の調査によれば、日本における家庭内の介護のうち約3分の2が老々介護に該当します。特に要介護者の年齢が75歳以上になると、介護者も70歳以上である割合が顕著に高まっています。
| 年代 | 介護世帯割合 |
|---|---|
| 60代が介護者 | 約20% |
| 70代が介護者 | 約35% |
| 80代以上介護者 | 約10% |
老々介護の割合は年々増加しており、認認介護も同様です。2000年代初頭には約3割だった老々介護も、現在は過半数を大きく越える社会問題となっています。今後も高齢化の進行に比例して増加が見込まれています。
老々介護が増加した背景-高齢化社会の進展と社会構造の影響
老々介護が拡大した主な背景には、日本の平均寿命の延伸、高齢化率上昇、そして核家族化の進展が挙げられます。子供世代が独立し、地方や都市部で離れて暮らす世帯が増えたため、高齢夫婦のみ、あるいは単身世帯が増加しました。
主な要因は以下の通りです。
-
高齢化:高齢者人口が総人口の約3割となり、介護の担い手も高齢者となるケースが増加
-
平均寿命の延伸:要介護期間が長期化しやすくなった
-
核家族化・独居増:家族形態の変化により、介護の支援者が少なくなる傾向
-
認知症高齢者の増加:認認介護による共倒れリスク拡大
-
経済・社会的負担の増大:身体的・精神的負担に加え、介護費用や生活費の問題も深刻化
このように、社会の構造的変化と人口動態の変化が老々介護問題の拡大の根底にあります。現状をきちんと理解した上で、適切な支援や制度の活用が求められています。
老々介護の具体的な問題点と多角的課題分析
身体的・精神的負担の実態-介護者の健康リスクとストレス
老々介護において、介護者にのしかかる負担は極めて大きく、身体面・心理面ともに無視できません。高齢者が高齢者を支える状況では、自分自身も健康リスクを抱えており、体力や筋力の低下で要介護者の身体介助に苦労する場面が多くみられます。長時間に及ぶ介護による慢性的疲労や慢性疾患の悪化、転倒やけがのリスク増加が現実的な問題です。
精神的側面では、閉塞感や孤独、無力感が積み重なりやすいです。介護者が十分な相談相手や支援を得られないと、心の健康にも大きな影響を受けやすくなります。厚生労働省の調査によると、老々介護世帯の多くが「ストレスを感じている」と回答しており、適切なサポートやサービスの利用が不可欠です。
介護者の健康管理で重要なポイント
-
定期的な健康チェックを受ける
-
周囲や地域包括支援センターへ早めに相談する
-
適度な休息と気分転換の時間を確保する
共倒れリスクの深刻さ-介護放棄や事故が起こる背景と防止策
老々介護では「共倒れ」のリスクが顕著です。高齢者同士の同居や夫婦の介護ケースでは、双方が要支援・要介護状態に至るケースも珍しくありません。主な背景には、身体的・精神的負担の累積だけでなく、経済的理由や社会的孤立、認知症の進行などが挙げられます。
【共倒れ・事故が起こる要因】
-
長期間の介護による心身の限界
-
経済的な余裕のなさや社会資源の未活用
-
緊急時対応が困難な環境や支援体制の不足
-
認知症による適切な判断力の低下
高齢化が進み、こうしたリスクは今後も増加する傾向にあります。事故や介護放棄を防ぐには、見守りサービスや訪問介護の導入、地域支援ネットワークの活用が鍵となります。定期的な見守りや福祉サービスの利用によって、日常生活の安全性を高めましょう。
認認介護における特殊リスク-認知症同士の介護の危険性
認認介護は、介護する側もされる側も認知症状態にあるケースです。判断力の低下・記憶障害が重なることで、突発的な事故やトラブルのリスクが非常に高まります。事例としては、薬の飲み忘れや誤用、火の不始末による事故、徘徊による失踪など深刻な事態が発生しています。
認認介護のような特殊リスクに対応するには、状況を正しく把握することが不可欠です。地域包括支援センターを早期に活用し、ケアマネジャーや医療機関による定期的な状態確認、住宅改修や見守り機器の導入も積極的に検討しましょう。社会資源の活用と早めの相談が支援体制確立の第一歩です。
【認認介護時の注意点】
-
必ず複数の支援サービスを組み合わせて利用
-
緊急連絡網や見守りシステムの導入を検討する
-
周囲の家族や専門家とこまめに情報共有を行う
老々介護を支える社会資源と制度活用方法
介護保険制度の基礎と申請の流れ-対象者の認定基準からサービス内容まで
介護保険制度は、40歳以上の方が対象となる公的な保険制度です。主に65歳以上の高齢者や特定疾病に該当する40歳以上の人がサービスを利用できます。要介護認定を受けることで、自宅での生活支援や介護施設利用など、幅広いサービスが使えるのが特徴です。申請から認定までの流れは次のとおりです。
- 市区町村の窓口に申請
- 訪問調査と主治医意見書の提出
- 介護認定審査会による審査
- 要介護度の認定と通知
申請は自分だけでなく家族やケアマネジャーでも行えます。介護保険サービスを利用することで、家族だけに頼る負担を軽減できる点が大きなメリットです。利用できるサービスは訪問介護・デイサービス・福祉用具の貸与や住宅改修など多岐にわたります。自身の状態や家族状況にあった活用が大切です。
地域包括支援センターなど相談窓口の機能と活用の実際
地域包括支援センターは、高齢者のさまざまな困りごとや相談に無料で対応する窓口です。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが協力し、要介護認定や介護サービス利用の手続き代行、虐待防止・成年後見制度の紹介など、地域に密着した総合支援を行っています。
利用方法はとてもシンプルで、電話や直接訪問で相談が可能です。初めての介護、認知症への対応、共倒れの不安、介護費用や今後の生活設計まで幅広くサポートが受けられます。また、家族だけで悩みを抱える必要はありません。安心して活用することで、問題を早期に発見し対策につなげやすくなります。
| 相談内容 | 具体的な支援例 |
|---|---|
| 介護保険申請 | 申請書記入サポート、必要書類案内 |
| 認知症・健康相談 | 専門職による健康相談 |
| 経済的困難 | 福祉サービス・助成金案内 |
| 家族関係や虐待 | 面談調整、適切な機関紹介 |
在宅介護サービスと介護施設の種類と選び方-訪問介護・デイサービス・ショートステイ・特養など
介護サービスには、「在宅介護」と「施設介護」があります。老々介護を続ける上では、各サービスの違いと選び方を理解することが大切です。
| サービス名 | 概要・特徴 |
|---|---|
| 訪問介護 | 介護スタッフが自宅に訪問し、生活支援や身体介助を行う |
| デイサービス | 日中施設で入浴・食事・機能訓練などを受ける通所型サービス |
| ショートステイ | 一時的に介護施設で宿泊・生活をサポート。家族の休息や一時不在時に活用 |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 常時介護が必要な方の長期入所施設で、入居には要介護度などの条件がある |
強調したいポイントは、利用者や家族の状況により最適なサービスは異なることです。サービス選びでは、要介護度・費用・自宅からの距離・家族の希望などを総合的に検討しましょう。いざという時に自治体やケアマネジャー、支援センターへ早めに相談すると安心です。
老々介護の負担軽減に向けた家族・親族の具体的行動
家族間の役割分担とコミュニケーション-介護者間の負担分散を図る方法
老々介護においては一人の家族に負担が偏りやすく、共倒れやストレス増加が深刻な問題となります。家族間できちんと役割分担を行い、こまめなコミュニケーションを取ることが不可欠です。
役割分担を明確化するには、定期的な家族会議やグループLINEでの情報共有が効果的です。それぞれの家族の得意分野や生活リズム、健康状態を考慮し、無理のない範囲で担当を割り振ることが重要です。
下記のポイントを押さえることで、介護の負担分散が実現できます。
-
定期的な家族会議で現状・課題を確認
-
各自ができる支援をリスト化し、負担を見える化
-
協力できる範囲を話し合い、無理なくサポートする体制づくり
家族内ルールを作り、話し合いがしやすい雰囲気を心がけることで、介護による心身への負担を軽減することができます。
孫や娘ができる支援と関わり方のコツ-世代を超えた介護参加の重要性
孫や娘など若い世代の参加は、介護する側の孤立感を和らげ、被介護者の心理的安定にもつながります。世代や家庭環境に合わせた関わり方を工夫することで、それぞれが力を発揮できます。
例えば、孫は遠隔地に住んでいても、定期的な電話やビデオ通話で声をかけ、高齢者の認知症予防や心のケアに貢献できます。娘や息子は、必要に応じて週末だけ訪問する、定期的に買い物や掃除をサポートするなど、無理なくできる範囲から始めるのがおすすめです。
家族それぞれの状況に応じて、以下のような工夫が有効です。
-
孫の訪問やメッセージで被介護者の心身機能の維持
-
離れて暮らす家族は買い物代行や事務手続きを担当
-
できる支援を細分化し、みんなで役割を持つ
こうした家族全体の意識づけや参加が、老々介護の大きな支えとなります。
介護教室や見守りサービス利用による支援ネットワーク構築
家族だけで介護を抱えこまず、地域の介護教室や見守りサービスを利用することで、支援ネットワークを拡大することができます。
介護教室では正しい介護方法の知識や、認知症への接し方、福祉サービスの紹介など多彩な情報を得られます。また、見守りサービスや地域包括支援センターの活用は、専門スタッフと連携しながら介護負担を分散できるため、心の負担軽減にもつながります。
| 支援サービス名 | 主な内容 | 利用メリット |
|---|---|---|
| 介護教室 | 介護方法・制度・心のケア学習 | 正しい知識で安心して介護できる |
| 見守りサービス | 定期的な安否確認・緊急連絡体制 | 危険時もすぐに対応できて安心 |
| 地域包括支援センター | 相談・情報提供・サービス利用の支援 | 専門家によるアドバイスが受けられる |
家族の負担軽減には、こうした外部リソースも積極的に活用し、無理なく続けられる介護体制を整えることが大切です。
老々介護に伴う経済面の課題とその解決策
老々介護中にかかる主な費用の実態-在宅介護と施設介護のコスト比較
老々介護では経済的負担が大きな問題となりやすく、どのような形態で介護を行うかによっても月々の支出が異なります。在宅介護の場合、主な費用は介護サービスの利用料、医療費、生活用品、福祉用具レンタル費などで構成されます。施設介護では、入居一時金や月額利用料、生活費、医療費などが必要です。
下記に在宅と施設でのお金の内訳と平均値を示します。
| 区分 | 主な費用内訳 | 月額平均費用(概算) |
|---|---|---|
| 在宅介護 | 訪問介護、デイサービス、食費、医療費、福祉用具 | 約7~15万円 |
| 施設介護 | 入居一時金、月額利用料(食事・介護費込)、医療費 | 約15~25万円 |
上記は目安となり、サービス内容や本人の状態によって増減します。在宅介護でも介護度が高ければ通所サービスの回数や福祉用具が増え、負担が重くなります。施設介護では、初期費用と月額の両方を事前に把握することが重要です。
公的助成と民間保険の活用法-費用負担軽減の具体的対策
介護の経済的負担を軽減するためには、公的な助成制度や保険の活用が有効です。介護保険制度では、要介護認定を受けることで多くのサービス費用が1~3割負担で利用でき、各自治体の助成金や独自補助もあります。
特に知っておきたい主なサポートとしては
-
利用額に応じた高額介護サービス費の払い戻し
-
福祉用具購入費の助成
-
住宅改修の補助
-
医療費控除
などがあります。手続きは市区町村の窓口や地域包括支援センターで案内されており、書類や診断書が必要な場合もあります。
また、近年増えている民間の介護保険は、要介護状態になった際に一時金や年金形式で給付を受けられる商品も多く、将来的な備えとして加入を検討する人が増えています。
家計管理と備えのためのポイント-介護生活を見据えた経済計画
老々介護のリスクに備えた家計管理は不可欠です。急な支出に対応できるよう、日常生活費の見直しや予備資金の準備が大切です。
特に意識すべきポイントは下記の通りです。
-
毎月の支出内容を定期的に見直す
-
定期預金や積立型保険などで緊急時の資金を蓄える
-
介護サービス利用の見込みや上限額を事前に確認
-
必要に応じて専門家(ファイナンシャルプランナーなど)に相談
将来設計を具体化することで、介護による経済的な悩みや不安を抑え、家族全体の安心にもつながります。日々の生活と並行して、早めの備えを考えていくことが重要です。
介護現場から見る実例とケーススタディ
老々介護における成功事例の紹介-負担軽減と笑顔を生む工夫
高齢の夫婦による老々介護では、体力や精神的な負担が大きくなりがちですが、身近な工夫で日常が明るく変わる事例が増えています。
主な成功ポイントは下記の通りです。
-
介護サービスの積極的な利用:デイサービスや訪問介護を活用し、介護者の休息時間を確保することで、心身の負担軽減を実現。
-
適切な福祉用具の導入:手すりや電動ベッドを活用して、介護動作が無理なく行えるよう工夫し、転倒リスクを減少。
-
地域交流や相談の場の活用:包括支援センターなどで専門職へ気軽に相談し、不安や孤立感の解消に成功。
特に、サービス利用に踏み切った家庭では、夫婦双方に笑顔やゆとりが生まれやすくなったという声が多く聞かれます。
実際の負担軽減実践例・アイデア・ポジティブな変化の体験談
以下のようなアイデアが実際に負担軽減に役立っています。
| 工夫・取り組み | 変化・成果 |
|---|---|
| 定期的な訪問介護の申込 | 介護時間の削減、夫婦に会話や趣味の時間 |
| 食材宅配サービスの導入 | 食事準備の手間が減り、栄養管理も向上 |
| タブレット端末の活用 | 遠方の家族や専門家と連絡が取りやすい |
| 介護予防体操の参加 | 健康状態の維持と気分転換に効果 |
このような取り組みで、介護者が無理せず支え合える環境が整っています。
認認介護の課題解決を図った実践例-専門的視点からの対応策
認知症を持つ高齢者同士が介護し合う認認介護は、従来の介護以上に課題が多い領域です。専門的なアプローチとしては、以下の対応策が挙げられます。
-
早期の認知症診断と適切なケアプラン作成
-
地域包括支援センターの専門スタッフによる定期的な見守り
-
緊急時にも対応可能な連絡体制の構築
特に、介護保険を利用した通所サービスやショートステイの併用により、家庭内でのトラブルや共倒れのリスクを抑えた事例が注目されています。認認介護世帯では、周囲の支援を積極的に取り入れることが持続可能なケアの鍵です。
認知症同士の難度高いケースでの具体的な工夫・介入方法
認認介護の現場で有効だった対応方法を紹介します。
| 工夫・サポート内容 | 得られた効果 |
|---|---|
| 定時に服薬確認や生活リズムの管理 | 混乱や体調不良の予防に寄与 |
| 訪問介護職による見守り・声かけ | 危険行動の抑止と安心感の向上 |
| 認知症対応型デイサービスの利用 | 外出機会の確保、家族のストレス減 |
| 緊急連絡カードの活用 | 万一の際の迅速な対応に役立つ |
認認介護はリスク管理が極めて重要ですが、工夫次第で安定した生活が実現可能です。
世帯別による課題と対応の違い-共倒れ回避の現場ノウハウ
世帯構成によって老老介護や認認介護の課題や対応策は異なります。特に二人暮らしの高齢世帯や三世代世帯では、リスクの種類や対応ポイントが大きく変わります。
-
二人暮らし世帯:介護者と被介護者双方が高齢のため、体調不良時に支え合いが困難。定期的な外部サービス導入や近隣との連絡体制が重要。
-
三世代同居世帯:子や孫の存在が緊急時の支援や相談のカギ。役割分担とサポート体制の明確化で負担を分散する工夫が求められる。
-
独居に近い世帯:近隣住民や自治体との連携強化で孤立を防止。
下記リストは、世帯構成ごとに重視すべきポイントです。
-
定期的な健康チェックと緊急連絡体制の確立
-
自治体サービスや支援団体へのこまめな相談
-
無理をせずプロの手を借りる勇気を持つ
身近なリスクと現実的な対応をセットで考えることで、共倒れは十分に防げます。
老々介護に関する情報収集と信頼できる情報源の見極め方
公的機関や専門家の情報活用法-情報の信頼性と鮮度を確保する方法
老々介護について正確な情報を得るには、信頼できる公的機関や専門家の情報を活用することが重要です。主な公式情報源は以下の通りです。
| 種類 | 情報源の例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 行政機関 | 厚生労働省、各自治体 | 最新の制度やサービス、統計データを公式に公開 |
| 専門機関 | 地域包括支援センター、介護支援専門員 | 現場の支援やプロのアドバイスを受けられる |
| 公的保険窓口 | 介護保険サービス窓口 | 介護保険の申請や利用に関する情報を提供 |
最新情報を確認するポイント
-
公式HPや広報誌、相談窓口を定期的にチェック
-
複数の情報源で内容を照合
-
専門家の監修記事や自治体のパンフレットの活用
信頼できる情報は、不安やトラブル回避に欠かせません。大切な制度やサービスの詳細は、必ず公式情報を確認しましょう。
信頼できる情報の見極め方・公式の情報源やその利用手順
信頼できる情報かどうかを判断するには、情報発信元の確認と最新性のチェックが必須です。
信頼性の高い情報の見極め方
- 発信元が公的機関や専門家であるか確認
- 情報の発信日や更新日を必ず確認
- 内容が具体的で根拠が示されているかチェック
公式情報源の利用手順
-自治体の公式HP、厚生労働省の統計ページから該当情報を探す
-情報に不明点があれば電話や窓口で直接問い合わせる
-必要に応じて地域包括支援センターや介護相談サービスを活用
最新の情報を正確に把握することで、介護環境の変化にも素早く対応できます。
地域別の支援体制の調査と活用-地域の特徴に応じた対応を得る
老々介護の支援体制は地域によって異なります。支援サービスや取り組みの内容を事前に調査し、地域の特徴に合わせた活用が必要です。
地域の取り組み・サービス比較表
| 地域 | 主な支援サービス | 特徴 |
|---|---|---|
| 都市部 | デイサービス、訪問介護、地域包括支援センター | サービスが充実し選択肢が広い |
| 地方 | 地域密着型の訪問支援や移動サービス | 人手やサービスに限りがあるが、密な支援体制 |
サービスの探し方
-
各自治体の公式HPで地域サービス一覧を確認
-
地域包括支援センターや在宅介護支援センターに相談
-
町内会や福祉団体から情報提供を受ける
利用可能なサービスを見極め、自宅から通いやすい支援や経済的な助成制度も積極的に活用しましょう。
地域ごとの取り組み・サービスの探し方・自治体の違いなど具体策
自治体ごとに利用できるサービスに違いがあるため、事前に確認することが重要です。
具体的な探し方と活用ポイント
-
市町村の福祉課や高齢福祉担当窓口でパンフレットをもらう
-
各種サポートの受付窓口や相談先を一覧で把握
-
介護保険認定窓口に直接相談して最新の支援体制を確認
自治体による主な違い
-
サービスの種類や費用負担の割合
-
独自の福祉サービスや助成金制度の有無
-
地域密着の介護予防教室や生活サポート事業
家族だけで悩まず、地域の支援ネットワークを積極的に活用しましょう。
介護者自身が実践できるメンタルケアと健康管理
介護を担う家族の心身の健康管理は、老々介護においてとても重要です。負担やストレスの軽減に努めることで、無理なく介護を続けられます。
日常の自己ケアポイント
-
規則的な生活・バランスの良い食事と十分な休息
-
日々の簡単なストレッチや散歩など軽い運動
-
趣味やリフレッシュできる時間を意識してつくる
ストレス軽減のためのリスト
-
周囲の家族や友人と悩みを共有する
-
介護者向けの相談窓口やサポートグループを活用
-
プロによるメンタルヘルス相談やカウンセリングを検討
自分の体調や気持ちの変化に早めに気づき、必要なときは専門家へ相談することで、共倒れや介護疲れを防ぐことができます。お一人で抱え込まず、サポートを上手に利用しましょう。
よくある質問Q&Aで疑問を解消する
老々介護の意味や現状に関する基本質問
概要や用語解説・現状データに基づく回答例
老々介護とは、高齢者同士、たとえば75歳以上の夫婦や家族が互いに介護を担う状況を指します。高齢化が進行するなか、2020年代には介護が必要な家庭の約7割で主要な介護者が65歳以上となり、「老老介護」の割合が増加しています。特に認知症や様々な健康リスクが高まる世代において、身体的・精神的な負担が大きいのが特徴です。英語では「elderly care by the elderly」と表現されますが、日本特有の深刻な社会課題として認識されています。現状においても介護問題は拡大し、家族単位で対応せざるを得ないケースが目立ちます。
主なポイント:
-
高齢夫婦や親子間での介護が顕著に増加
-
認知症や身体機能低下による介護負担の複雑化
-
身近な現象として生活の質や家族関係にも影響
介護負担や支援制度に関する具体的な相談事項
支援情報や制度について頻出する質問・その詳細な解説
老々介護には介護保険や各自治体のサポートが活用できます。申請を行えば、要介護認定を受けて多様なサービス(訪問介護、デイサービス、福祉用具の貸与など)が利用可能です。支援センターでは介護者向けの相談窓口も設置されており、経済的な助成・負担軽減策なども案内されています。介護費用の目安はサービス内容や利用頻度によって異なりますが、「お金がない」「限界」という声にも丁寧な個別対応が進められています。
| よくある相談内容 | 解説 |
|---|---|
| 介護保険の利用条件は? | 65歳以上、もしくは40歳以上で特定疾病の方が対象です。 |
| 支援サービスには何がある? | 訪問介護、ショートステイ、福祉用具レンタルなど多岐にわたります。 |
| 経済的負担を軽減する方法は? | 所得や要介護度に応じて自治体から多様な助成金が提供されています。 |
家族間の役割や介護者の健康に関する質問例
実際の家族相談・分担や健康維持の現場疑問に寄り添う情報
高齢夫婦間での介護や「認認介護(認知症同士の介護)」では、どちらも無理をして心身ともに疲弊してしまうことが少なくありません。家族の中で分担が偏ったり、「娘ばかり」に負担が集中するという相談も多く寄せられます。日々の生活では介護者の健康管理が重要視されており、ストレスや孤立感の軽減には地域包括支援センターや家族会、相談窓口の利用が推奨されています。
よくある健康管理ポイント:
-
無理をせず適切に休息を取る
-
家事や介護の分担を話し合う
-
定期的な健康診断やリフレッシュの機会を持つ
身近な支援に目を向け、決して一人で抱え込まず、外部サービスや専門家と連携することで「共倒れ」のリスクを回避できます。